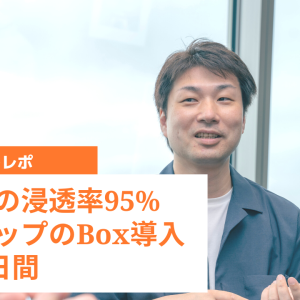書面からデジタルへの大移行。裏で営業現場を支えたメンバーの底力。
変革を怖がらず、時代の流れにいち早く適応する。その決断の速さはいつもディップの成長を後押ししてきた秘訣であり、現在の規模になってもその風土は健在。今回はコロナ禍で、営業の業務フローをアナログからデジタルへ移行させた中心である事業管理室のメンバー、安齋に話を聞いた。
会社としての最重要フローを、紙からデジタルへ。
冨岡:営業さんの命とも言えるクラアイントからの申込書。その管理フローが紙から業務アプリ構築サービス『kintone(キントーン)』のシステム上での管理になった今年。どんな流れでこのデジタル化は進んだのですか?
安齋:今年の1月頃でしょうか。営業部の会議で、コロナが本格的に危険視されてきたから現場全体でテレワークを推し進めよう!となったのが発端です。それを私たち事業管理室で前もってキャッチして、じゃあ営業部がそういった動きに切り替わるときに今の売り上げ処理などのフローのどこらへんに影響を受けるのか?現状のままだとまずい部分は?といったことを考え始めました。
冨岡:なるほど。時間的にもカウントダウンされているような状況で急遽始まったんですね。
安齋:紙でやりとりしていた申込書が、テレワークになってしまうと出せない。そういう状況になるのは会社的に致命的なので代わりのフローを考えなければと。今までは本当にアナログで。印刷した紙の申込書にお客様から捺印をもらって、それをスキャンしてPDF化。それが私たち事業管理側にデータとして送られてきて、そのデータを再度印刷して承認……という流れだったので、変更する必要がありました。
冨岡:結構めんどうというか、印刷も二重でしなきゃいけなかったり、これではテレワークに向きませんね。
安齋:本当に。でも、運がいいことに申込書のデジタル化に先駆けて、申込書と関わりのある、事業管理室で「帳票」と呼んでいる書類はkintone上での管理にすでに移行していたんです。事業企画統括部内にもともとkintoneを持ち込んだチームがあったので心強かったですね。そことも連携して、なるべくスムーズに移行できる体制を整えました。
冨岡:その結果、いつ頃に移行完了したんですか?
安齋:2月頭には旧フローが変わる旨を現場アナウンスして、2月中には現行フローに切り替わりましたね。
冨岡:それはすごいスピード感でしたね……!ディップの社風を感じます。
今までの当たり前を作り替える大変さ。
冨岡:そういったスピード感をもってやっていく中で、大変だったことってありますか?
安齋:大変だったというか、ネックだったのは内部統制的に問題なくWEBに切り替えられるかという点ですね。申込書はどうしても紙として残さなくてはならないというルールがあったので、そこを守った状態で、ということを考えていかなければなりませんでした。でもそこを、kintoneというシステム上で管理する、イコールいつでも印刷できる、紙面で残せるという今までと同等の仕組みが作れたので、暫定ではあるけれどこの火急の状況ではなんとかOKになりました。準備期間は約1ヵ月という短い中で、契約や内部統制に関連するいろいろな部署と審議を重ねましたね。
冨岡:実際に現場に今のシステムが導入されてからはどうでしたか?
安齋:kintoneに今のシステムをリリースしてからは、営業さんが使いこなせるようになるまで現場への浸透に力を入れていましたね。営業さんとしてもテレワーク時に出社しなくていい、というメリットがあるのでシステムの導入を前向きに捉えてくれていることはよかったのですが、導入初期は操作に不慣れなこともあったのでミスが発生しないように細かいケアをしていきました。
冨岡:具体的にどんなことをしていたんですか?
安齋:申込書の処理フローが滞らないように、最初は都度都度こちらから営業さん個人へアラートを出していました。「kintoneのこの画面から、次の承認ボタンを押してください」とか、電話越しに画面上での操作方法を伝えたり。営業部の管理職などは扱うツールも多いので、浸透するまでは丁寧にフォローすることを大事にしていました。
今までになかった経験を経て、組織も強くなった。
冨岡:ここまでお話を聞いてみて思ったのですが、デジタル化のアイデアっておそらく今までも挙がっていたと思うんです。でも、それはしなかった。だけど今回すごいスピード感で実現に至って、部としても異例なことだったんじゃないでしょうか。
安齋:そうですね。私たちの組織としての最重要課題は、会社の正確な売り上げを管理することです。絶対にミスがあってはならない部分。だから業務柄、保守的になりがちで何かを新しく始める時も、リスクはどうなの?問題が発生しないか?って欠陥がないかということに意識をとられる傾向にあります。
冨岡:なるほど、組織の性格と言うところですね。
安齋:でも、今回はコロナ禍の緊急事態ということもあって、リスクを考えることは大事だけど、今は運用可能なシステムをリリースできることが重要!っていう雰囲気が組織にもあったと思います。
冨岡:それは組織としては、今までにない経験を積めた機会だったということでしょうか。こういう仕事って、もっと上層部のマネジャークラスの方が指揮をとっているのかと思っていましたが、現場のメンバー達が個々で動いて実現されているというのもディップの風土ですね。
安齋:本当にそう思います。色々な関係部署の方がスピーディに動いてくれたからこそ約1ヵ月という期間で実現できたんだな、と。この経験を活かして現在の暫定的なシステムをさらにアップデートさせたものや、申込書以外のフローもデジタル化して、もっと現場が使いやすく、正確な数値が管理できるシステムを作っていけたらいいなと思っています。