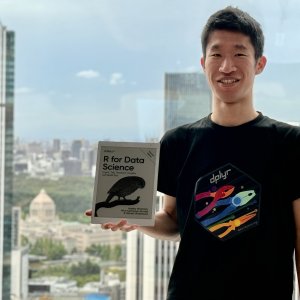新卒エンジニアの成長法則 ―― “分からない”を武器に変えるキャリアの第一歩
新卒エンジニアにとって「分からない」は弱みではなく、成長のきっかけです。本記事では、配属2日目のタスクで60件ものフィードバックを受け取った新人エンジニアが、その経験を通じてどのように学び、チームを成長させ、テックリードを目指すようになったかを紹介します。これから社会に出るエンジニアにとって、成長のヒントが得られるはずです。
新卒1年目の成長の鍵は「分からない」を自覚すること

田中:藤崎さんがテックブログで発信した「Andoroidエンジニアの新卒1年目振り返り」の記事を読みました。スクラム開発の立ち上げメンバーへの加入や、Jetpack Composeの導入など、様々なことを経験を積んだ濃密な1年目でしたね。
藤崎:そうですね、技術的な学びだけでなく、チーム開発やコミュニケーションの重要性など、エンジニアとしての総合的な成長を実感できた1年間でした。でも最初は「これは何を意味するんだろう?」「どういう機能なんだろう?」と分からないことだらけで、苦労しました。
配属2日目にバグ修正タスクを担当したんですけど、プルリクエスト(PR)で先輩方に数多く指摘を頂いた結果、最終的にはコメント数が60件にもなって。
田中:普通なら心が折れそうですね。
藤崎:もちろん最初は自分でも驚きました。でも今振り返ってみると、この経験が自分の1年間の挑戦や成長の糧になっている気がします。バグ修正が他の機能に与える影響を考慮することの重要性や、コードレビューの意義を学ぶ、貴重なきっかけになりました。
田中:確かに、大規模サービスならではの学びですね。そんな中でこの経験が挑戦や成長の糧になったというのは?
藤崎:配属されて最初に携わった『はたらこねっと』というサービスは、歴史が長く、コードベースの規模も大きく、ドメイン知識が膨大だったんですね。でも先輩から60件のフィードバックを頂けたことで、その後は自らコードレビューに参加して、積極的にコミュニケーションを取るようになりました。
他にもすぐに周りの先輩に質問したり、分からない部分は、そのプルリクエストを作成した人に直接聞く。そうすると、他の人のコードの意図や背景、ドメイン知識を効率的に吸収できるようになって、実際に入社当初と比べて、コードレビューに参加する頻度は半年間で3倍くらいに増えたと思います。
田中:学びをすぐ実践できるのは凄いですね。でも何が藤崎さんを突き動かしたのでしょうか?
藤崎:単純に「自分が成長したい」という気持ちが一番強かったからですかね。もちろん、チームのメンバーを助けたいという気持ちもありましたが、個人的には自分の知識を増やすためのインプットの機会として捉えていました。
周りの先輩のサポートもあり、自分はコードレビューは、他のエンジニアから直接話を聞ける貴重な機会だと考えていました。
田中:実際にコードレビューに取り組んでみて、何か変化はありましたか?
藤崎:まず、知識が格段に増えました。そして、何よりもコミュニケーションのハードルが大きく下がったと感じています。コードレビューを通じて普段あまり話す機会のない人とも接点ができ、気軽に質問したり相談したりできる関係性が築けました。インターネットで調べるだけでは得られない、コードの「意図」や「背景」といった深い知識を得られたことは、エンジニアとしての成長に大きく寄与したと思います。
田中:素敵ですね。人から学び、関係を築く、そんな藤崎さんだったからこそ『はたらこねっと』のスクラム開発の立ち上げメンバーに選出されたのかなと思いました。
スクラム開発への挑戦と「知識共有」の価値

藤崎:ありがとうございます。実際に自分が一番入社歴が浅かったのもあって、周囲からは「分からないことはどんどん聞いて、その知識をチーム全体で共有してほしい」という期待をいただいていました。そう言ってもらえるのも、コードレビューを通じたやり取りが大きかった気がします。
田中:確かに、先ほどのコードレビューでの積極的なインプットが、まさにスクラム開発で求められる役割と合致していますね。スクラム開発が始まったのは1年目の8月くらいですよね?実際にやってみてどうでした?
藤崎:新しい技術や手法に触れるのが好きなので、純粋に楽しみでした。それに就活生の時に思い描いていた、プロダクトを「いいものにしよう」という共通の目標に向かって、チーム全員が同じ方向を向いている感覚を今まで以上に強く持てるようになりました。そしてスクラム開発の途中、11月頃に自分の役割が変わったことが、自分にとってはまた大きな転機になりました。
田中:藤崎さんがテックリードに近い立場になった時期ですね。チーム編成で自分以外のメンバーは『はたらこねっと』の開発に携わるのが初めてという状況で。自身の開発と並行して、知識の共有を行うのは大変だったのではないでしょうか?
藤崎:そうですね、時間的な制約も大きかったですし、人に教える難しさも感じました。特に、最初のスプリントでリリースしたインクリメントで、これまでにないほど多くのバグが発生してしまったんです。その時、「プロダクトの品質が落ちてしまったのは、自分の知識共有が不足していたせいだ」と、強い責任を感じました。
プロダクト全体の品質を考えた時に、チーム全体の知識レベルを高める必要があると痛感しました。そこから「自分も成長しながら、周りのメンバーも一緒に成長させていこう」という意識が強くなりましたね。
田中:だからモブプログラミングを積極的に取り入れてたんですね。
藤崎:そうですね、相手の理解度や成長を考えて、ただ指示するだけでなく、一緒に考えたり、相手の意見を尊重しながら進める点を大事にしていたので、モブプログラミングはぴったりな進め方でした。
それに人に教えるためには、「意図」を明確に言語化する必要がありますよね。それが、結果的に自分のコードの質を高めることに繋がったと感じています。 以前は曖昧だった部分も、人に説明することを意識することで、より明確に、論理的に考えられるようになりました。
実は、自分は元々、言葉で表現するのが苦手なタイプだったのですが、スクラム開発を通じてコミュニケーション能力が飛躍的に向上したと感じています。
成長の先に描くテックリード像

田中:自ら学び、周囲に知識を共有する中で、また自分も成長する。それが藤崎さんが大きな挑戦を続けていた秘訣のように感じました。それを踏まえて次に藤崎さんが挑戦したいことはありますか?
藤崎:そうですね、スクラム開発を通じてエンジニアだけでなく、PO(プロダクトオーナー)やデザイナーなど、様々な職種の方と密に関わる機会が増えたことで、視野も広がりました。デザイナーと一緒にJetpack Composeの導入に取り組めたのも、自分一人では得られなかった大きな成長によるものだと感じています。そういった経験があって、自分の技術でチームを強くし、プロダクトを成功に導く「テックリード」という役割を、引き続き探求していきたいです。
田中:藤崎さんが目指す「テックリード」とは?
藤崎:テックリードには、プロダクト全体のアーキテクチャや設計など、技術的な意思決定をする力が非常に重要だと感じています。一つの技術に閉じこもるのではなく、全体を見据えて最適な技術を選択する視点。そして、技術だけでなく、ビジネス的な側面も理解し、プロダクトにとって何が最適かを判断する力が求められると感じています。
今は新しいプロジェクトにアサインされ、チームでは、新しい技術であるKMP(Kotlin Multiplatform)を導入しています。自分たちで意思決定をする場面が非常に多く、まだ情報も少ない中で試行錯誤しながら開発を進めています。そんな中でも、メンバーと知識を共有し、チーム全体の開発力が底上げされていく。そんなテックリードを目指しています。
田中:まさに藤崎さんの一つひとつの挑戦が紡いだテックリード像ですね。では最後に、ディップで働く未来のアプリエンジニアに向けてメッセージをお願いします。
藤崎:ディップのエンジニア組織は、常に変化し、成長し続けています。「今までこうだったから」という考え方ではなく、「もっとこうしたら良くなるんじゃないか」と、常に新しいことに挑戦できる環境だと思います。もしディップで働くことになったら、積極的に行動し、コミュニケーションを取ってくれる方だと嬉しいです。
質問したり、フィードバックしたりすることで、チーム全体の知識共有や活性化に繋がります。自分の成長がチームの成長に、そしてプロダクトの成長に繋がるという好循環を生み出せる、そんな方と一緒に働きたいです!