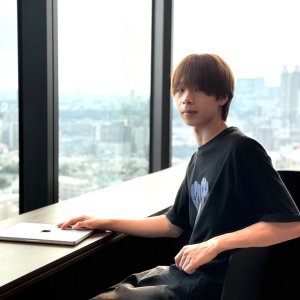未来を見据えた開発をする。EM視点で考えるディップの開発本部が目指す「かっこいい組織」とは?
目の前の課題を解決するだけでなく、その先にある未来を見据えた開発をする。それが、木村さんの思うディップの開発本部が目指す「かっこいい組織」。その実現のためには、一人ひとりのメンバーが自ら考え、行動する主体性が不可欠となります。今回は3つのチームを兼務し、組織の変革を推進する木村敏也さんにインタビュー。メンバーの「人」を起点とした組織作りの舞台裏と、その先に描く開発本部のビジョンについて、ナラティブに迫ります。
SESから事業会社へ。長く続くプロダクトを育てたい
岩城:木村さんは現在、複数のチームを兼務されていると伺いました。まずは、現在の役割について教えていただけますか?
木村:はい。現在は『バイトル』事業に関わる3つの部署で課長を務めています。具体的には、バイトルグロース課、第一バイトル開発部、そしてOps1課です。EMとしてチームメンバーのマネジメントや育成、組織作りを担う一方、Ops1課ではテックリードをしています。部署によって役割が少しずつ違う、少し複雑な体制かもしれません。
岩城:ディップに入社した経緯を教えてください。
木村:前職まではSESのエンジニアとして働いていました。そこでは、プロジェクトごとにチームが解散することがほとんどで、せっかく育てたプロダクトやチームがリセットされてしまうことに、もどかしさを感じていたんです。もっと腰を据えて、一つのプロダクトと長く向き合いたい。10年経ったらどんな景色が見えるんだろう、と。そうした思いから、事業会社であるディップへの転職を決意しました。
岩城:3つのチームを兼務されるのは珍しいケースかと思いますが、このような体制になった経緯を教えていただけますか?
木村:入社時は『バイトル』の管理を主たる業務とするクライアントエンハンス課の課長でした。そこから求職者向け『バイトル』のカスタマーエンハンス課が統合してバイトルグロース課になり引き続き課長をしています。そして今年になって新規プロジェクトを実施するための部署が新設された時に今までの仕事を評価していただき、web課とOps1課の課長も兼務することになりました。
バラバラだったチームのベクトルを揃える「意味のある雑談」
岩城:マネジメントというポジションでディップに入社した時にどんな課題に向き合いましたか?
木村:現在の部署に着任した時、まず僕が向き合ったのは、メンバー一人ひとりの「仕事への向き合い方」でした。当時、メンバーがそれぞれ異なる方向を向いているような状態だったんです。「ディップにいます」「この部署にいます」「このシステムを作ってます」以上、という、言われたことを淡々とこなすような雰囲気でした。これでは、どんなに優秀なメンバーが集まっていても、その力が一つの大きなエネルギーになることはありません。そこで、まず始めたのが「僕たちは同じミッションを持った仲間なんだ」という意識を浸透させることでした。そのために最初に行ったのが、「意味のある雑談」です。
岩城:「意味のある雑談」ですか?
木村:はい。いきなり仕事の目標や課題について話すのではなく、まずは一人ひとりの「人」を知ることから始めました。じっくり時間をかけて1on1を行い、これまでの人生、過去の苦労話、仕事のどんな瞬間に喜びを感じるか、といったことを聞いていきました。面接のような感じです。
そうすると、その人がどういう状況で頑張れるのか、どういうことにやりがいを感じるのか、パターンが見えてくるんです。給料が高いと頑張れる人、褒められると頑張れる人、仲間と一緒だと頑張れる人、何をやっても頑張れない人…。色々なタイプがいます。過去のエピソードや部活の経験などを聞いていると、どういう傾向があるのかがわかってくる。
その上で、「じゃあうちの会社にはこういう課題がある。君が所属するこの部署では、こんな重要なシステムを扱っているんだ。それに貢献することは、君自身のこんなメリットにもつながるよね」という話を紐づけていきました。すると、最初はバラバラだったメンバーの意識が、少しずつチームの目的に向かっていくんです。
岩城:1on1を重ねることで、少しずつメンバーの意識が変わっていったんですね。
木村:ただ、メンバーは20人近くいるので、全員とじっくり1on1をするには時間が足りません。そこで、週に一度の定例会で、仕事とは直接関係ない雑談テーマを設けるようにしました。たとえば、「この夏休み、何をしたい?」とか、「最近面白かった技術は?」といった、メンバーが自由に話せる議題を出します。そうすると、ある人は毎回のように休みの話をするし、別の人はいつもAIコーディングの話をする。そういったフリートークから、それぞれの興味や人となりが垣間見える。僕は、これらをすべて「情報」だと捉えています。その情報を蓄積して、「この人と話すなら、この話題から入ってみよう」と会話のヒントにしたり、コミュニケーションのきっかけにしたりしています。また、全員で話す場だからこそ見えてくる情報もあります。みんなの前ではあまり発言しないけれど、チャットでは積極的に意見を出す人もいる。そうした行動パターンも、その人の個性として捉え、組織作りに活かしています。

「なぜそれをするのか?」を問い続け、仕事に「面白さ」を見出す
岩城:私から見た3部署は現在チームのベクトルが揃っているように感じます。次に「第2フェーズ」として取り組んでいることはありますか?
木村:そうですね、次のフェーズでは、「定性から定量へ」という視点をチーム全体で持てるように動いています。メンバーはみんな、日々の業務に一生懸命です。リリースに向けて「うぉ~頑張ったぞ!」と、目に見える成果を出す。周りから見れば「みんな頑張ってるね、キラキラしてるね」と見える。それは素晴らしいことなんですが、それだけでは不十分です。ビジネスの世界では、「その頑張りはどれだけの価値があるのか?」「どれだけ会社に貢献できたのか?」という、定量的な説明が求められます。メンバーが次に伸ばせるポイントですね。これまでは僕がメンバーからヒアリングして、彼らの頑張りを上層部に伝わるように料理して出していました。でも、それでは彼らの成長になりません。本当の意味でプロフェッショナルとして自立するには、自分でその「料理」ができるようにならなければならないからです。
岩城:それは難易度が高いですね。具体的に、どういう取り組みから始めているのですか?
木村:まず、開発計画の段階から「なぜ、この機能が必要なのか?」を深く考えるように伝えています。例えば、新しい機能を実装するとき、エンジニアは一番手っ取り早いやり方を選びがちです。でも、その機能がなぜ必要なのか、その先にお客様が本当に求めているものは何なのか、まで想像力を働かせることで、未来に備えたコードを仕込むことができる。すると、3ヶ月後に「やっぱりお客様からこういう要望が来たよ」と言われたときに、「マジっすか!?」となるか、それとも「大丈夫です、準備していましたよ」と30分で対応できるか、結果が大きく変わります。この「未来を読んで仕掛けておく」ことが、僕が考えるエンジニアの腕の見せどころであり、仕事の面白さだと思うんです。
岩城:それが、木村さんが前職のSESで感じた「プロダクトを長く育てる面白さ」にもつながっているのですね。
木村:まさにそうです。SESでは、どれだけ思い入れを持ってプロダクトを育てても、プロジェクトが終わればリセットされてしまう。それが悔しかったので、ディップという事業会社に転職しました。同じチームで、同じプロダクトに真剣に向き合い、10年後どうなっているかを見てみたかったんです。その面白さをメンバーにも味わってほしい。そのためには、目の前のタスクだけでなく、「なぜこのタスクが必要なのか」「この仕事が最終的にどういう価値を生むのか」を自ら考える習慣をつけさせたいんです。今はまだみんな戸惑っていますが、この取り組みが定着すれば、間違いなくチーム全体のレベルが底上げされます。
岩城: その「先に仕掛ける」という発想は、どのようにして生まれるのですか?
木村: 経験ももちろん大事ですが、最も重要なのは「どう見て、どう聞いて、どう話すか」というスタンスです。POや事業部の話を聞くときに、単に機能を満たすことだけを考えるのではなく、その先にいるお客さんの困りごとまで想像力を働かせる。例えば「レンガを積んでいる職人」の話のように、単にレンガを積むだけでなく、「教会を作って、町の人を幸せにする」という大きな目的を理解して仕事に向き合うこと。この丁寧さこそが、先に仕掛けることにつながります。
岩城: 丁寧に向き合うことで、仕事がより楽しくなる。
木村: そうですね。仕事がつまらないと感じるのは、「楽しもう」という努力をしていないからだと思うんです。人間には24時間平等に与えられていますが、そのうち8時間を「お金のためだけのつまらない時間」にし続ける人生はもったいない。環境や仲間も大事ですが、一番簡単に変えられるのは自分の考え方です。
岩城: 自分のスタンスを変えることが、仕事を楽しむ第一歩だと。
木村: その通りです。楽しく仕事に取り組んでいれば、自然と成果もついてきますし、誰にも損はありません。ゲームのレベル上げのように、苦しい期間もあるけれど、それを乗り越えた先にはボスを倒すという楽しみが待っている。そうした考え方で、仕事と向き合っています。

開発本部をもっと「かっこいい組織」に
岩城:そうした取り組みを通じて、開発本部全体をどのような組織にしていきたいですか?
木村:一言で言うと、もっと「かっこよくなりたい」ですね。僕たちがやっていることは、ディップの売上を支える重要な仕事です。だからこそ、経営者とも対等に話せる存在になりたい。経営者が見ている「数字」に、僕たちの「技術」や「努力」を紐づけて説明できるようになれば、それは本当の意味で会社にとって不可欠な存在になれる。そのために、まずは僕のチームがそのモデルケースになりたいんです。「うちのチームは、こういう取り組みをして、これだけの成果を出しています」という実績を示すことで、他の部署も「じゃあうちも真似してみよう」となる。そうやって、開発本部全体がレベルアップしていく。誰もが「ディップの開発本部はかっこいい」と憧れるような存在になりたいんです。
岩城:最後に、ディップの開発組織にはどんな人が合う、どんな人と働きたいと思いますか?
木村:「よかれと思ったことを、ちゃんと言える人」ですね。転職してくる皆さんは、外の世界の「常識」や「新しい風」をディップに運んできてくれる、貴重な存在です。僕たちはディップのルールしか知らないから、無意識のうちに非効率なやり方をしているかもしれません。そこに気づいたときに、「こうすればもっと良くなりますよ」と、臆することなく意見を言える人。そういう人と、一緒に働きたいです。その意見が、もしすでに試したことだったり、別の理由で難しいことだったとしても、「なるほど、そういう背景があるんですね」と理解した上で、一緒に改善策を考えてくれる。そして、もしそれがディップの誰も気づいていなかった良いアイデアだったら、その意見が組織全体を変えるきっかけになるかもしれない。新しい仲間と出会い、より良い未来のために意見をぶつけ合い、共に成長していく。それこそが、僕たちが目指す「かっこいい組織」を創り上げていく上で、何よりも大切なことだと考えています。