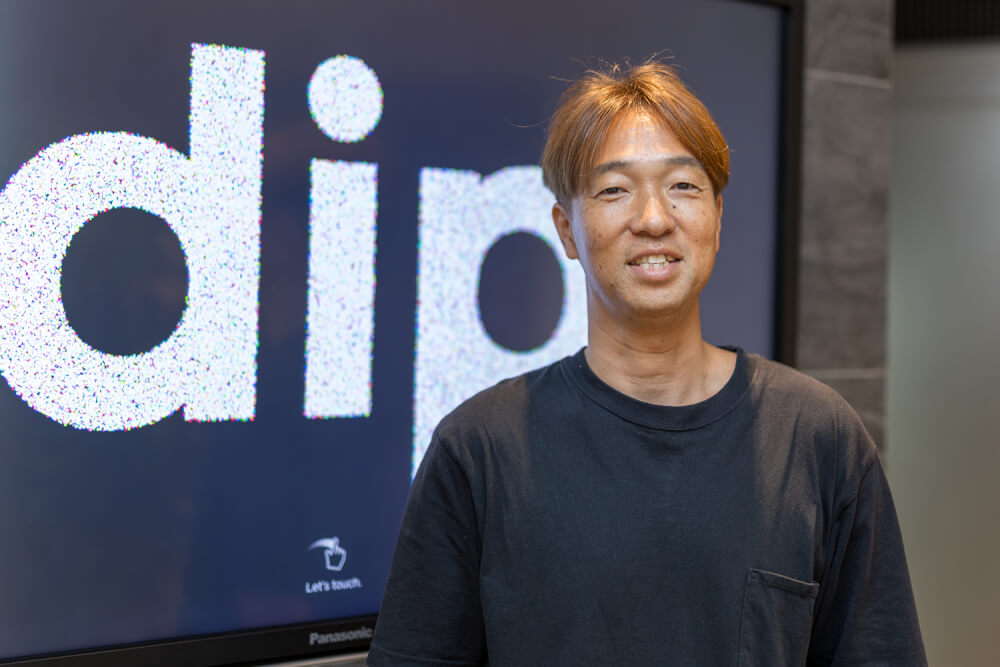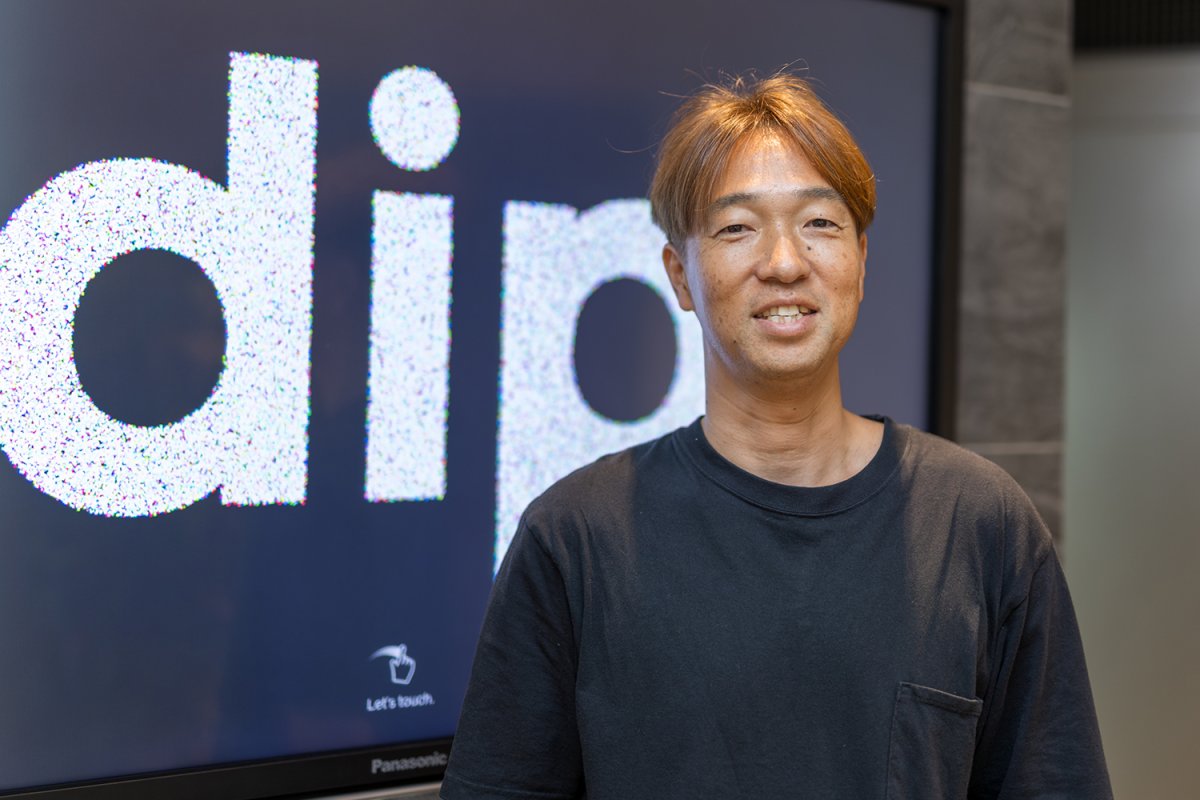
ユーザーに寄り添い、10年後も価値を生み続けるプロダクトへ。テックリードが新規プロジェクトの指針を描く。
転職を経て、様々な開発経験を積んできた宮川さん。業務系システム開発からコンシューマー向けサービスへとキャリアの軸を移した彼が、次に選んだ舞台はディップでした。 現在彼は新規プロジェクトのテックリードとして、その最前線に立っています。10年後も使えるプロダクトを目指す中で、彼が抱く「エンジニアとしての理想像」とは?そして、その挑戦の先に何を見据えているのでしょうか。これまでの経験からディップ株式会社での現在の仕事、そして未来の展望まで、そのキャリアストーリーに迫ります。
様々な経験を経てiOSアプリ開発のテックリードへ
岩城: まずは現在のご所属と担当業務について教えていただけますでしょうか。
宮川: 入社してしばらくは、『スポットバイトル』のワーカー向けアプリケーション開発を担当していましたが、現在は新規プロジェクトで、モバイルアプリ開発をしています。特にiOSアプリ開発のテックリードです。
岩城: 様々な開発経験をお持ちだとお伺いしましたが、これまでのキャリアについてもう少し詳しくお聞かせいただけますか?
宮川: 新卒で入社した会社では、5年間以上、携帯電話向けのアプリや組み込み開発を経験しました。その後、デジタル地図データやルート探索データを扱う会社でWebフロント・バックエンド、そしてiOS・Androidアプリ開発を7〜8年ほど担当しました。その次は、オンライン会議やオンラインイベントのプロダクトを開発する会社で、iOSアプリ開発を3年ほど経験し、ディップに至ります。
岩城: 非常に幅広いご経験ですね。たくさんの選択肢がある中で、ディップへの転職を決めた理由は何だったのでしょうか?
宮川: 過去の経験の多くが、社内利用者向けの業務系システム開発でした。より多くのユーザーに影響を与えるプロダクト開発に携わりたいという思いが強くなり、toC領域のサービス開発に興味を持つようになりました。
岩城: ユーザー数の多さが決め手になったと。
宮川: はい。それから、ディップが「労働力の社会課題解決」を目指している点にも惹かれました。社会課題を解決していくというアプローチは、非常にやりがいがあると感じました。
企画チームとの連携が生み出す「ユーザー視点」
岩城: チームではどのように開発を進めていますか?
宮川: 現在携わっている新規プロジェクトでも、以前携わっていた『スポットバイトル』チームでも、スクラム開発で進めています。なのでPOとは密接に連携していますね。エンジニアだけだと、どうしても一歩引いて「誰のための、何のサービスなのか」という視点を持ちづらくなることがあります。企画の担当者がユーザーのペルソナや課題を深く掘り下げ、そこからユーザーストーリーを組み立ててくれるため、ユーザーを意識した開発ができるようになりました。
岩城: 実際に企画との連携でどのような価値が生まれるのでしょうか?
宮川: 入社してから、改めてユーザー視点とは、企画チームと密に連携し、数字と向き合いながら、ユーザーの課題解決に貢献することだと実感しました。『スポットバイトル』を担当していた頃、直前キャンセル率が課題になっていたんです。企画担当者が様々な施策を考案し、それを開発チームが機能として実装することで、キャンセル率の低下に貢献できたことがありました。他にもアプリ初回起動時にオンボーディングを表示する機能を追加し、ユーザーが初回利用時に『スポットバイトル』というサービスについての理解を深められるようにするなど、さまざまな機能を作ってきましたね。ユーザーの課題解決に貢献できたと実感できるのは、大きなやりがいです。
岩城: 逆に、大変だった点はありますか?
宮川: ディップに入社するまで本格的なスクラム開発の経験がなかったので、スピード感には最初は苦労しました。1〜2スプリントという短い期間でバックエンドからフロントエンドまで機能開発を完了させる必要があり、ドメイン知識のキャッチアップも含めて必死に食らいついていきました。
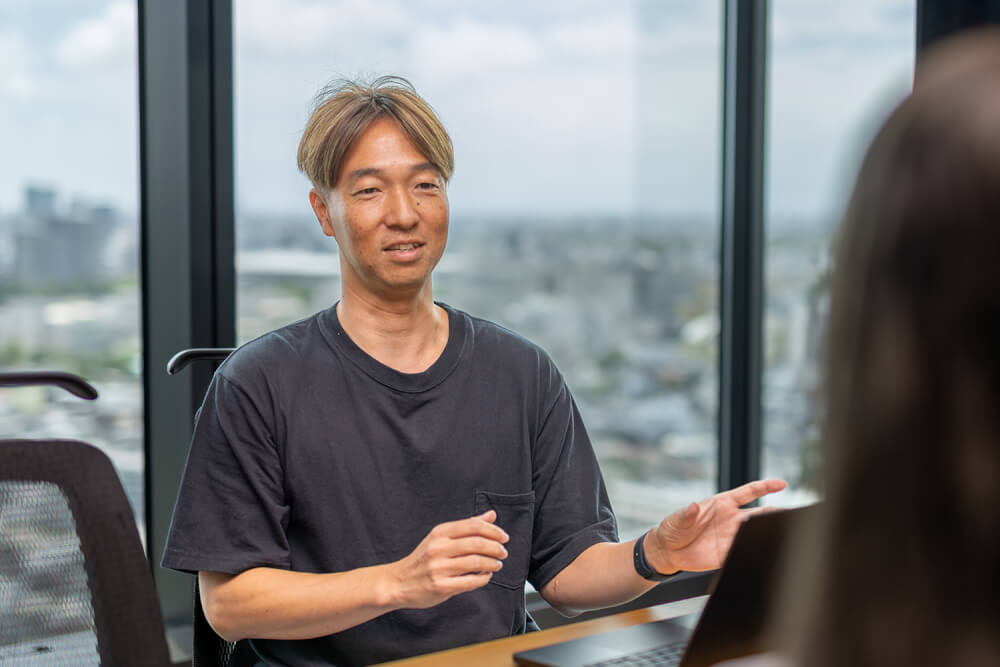
10年後も使えるサービスであるために
岩城: 『スポットバイトル』の担当から、新規プロジェクトのテックリードへと、役割が変わったとのことですが、その時の心境はいかがでしたか?
宮川: 新規プロジェクトではものすごい数のユーザーを抱えています。立ち上げのプロジェクトという責任の重さを強く感じると同時に、この仕事をやり遂げれば、ディップの中で自分の役割や居場所を確立できるのではないか、という思いもありました。エンジニアのキャリアとして見ても大きなチャンスだと感じています。
岩城: 新規プロジェクトではどのような目標を掲げていますか?
宮川: スクラムで開発を行ってきた今までの経験なども活かしつつ、チームを導くという役割に挑戦しています。プロジェクト開始時に、チームのメンバーそれぞれがこのプロジェクトで果たす役割、リーダーシップの宣言を行う機会がありました。私の宣言は「技術的な指針を明確にし、開発の方向性をぶれさせないこと」です。テックリードとして、アプリ開発領域における技術的な指針を定めること、Android/WebとUI/UXを統一すること、ユーザーの使いやすさとメンテナンス性の高いアプリを作ることを目指し、この先も進化していけるプロダクト開発をリードしていく役割を担っています。
岩城: 具体的には、どのような点を意識されているのでしょうか?
宮川: 「10年後も使えるプロダクト」を目指しています。そのため、モバイルアプリ開発においても、アーキテクチャやドメイン駆動設計のようなデザインパターンなどを導入することで、将来的な変更や機能追加に柔軟に対応するための土台を作ることを目指しています。
岩城: 非常に中長期的な視点での開発ですね。
宮川: はい。また、開発チーム内ではiOS開発をメインとしながらも、Kotlin Multiplatformの導入にもチャレンジしています。これまでのiOS開発の知見を活かしつつ、Androidチームと共通ロジックをKotlin Multiplatformで開発することで、開発効率の向上とチーム全体の技術力底上げに貢献していきたいと考えています。
岩城: 素晴らしいですね。仕事に対する向き合い方として、大切にされている軸はありますか?
宮川: エンジニアとして「ものづくり」をする以上、様々な技術課題に直面します。それらを「楽しみながら解決していく」というメンタルは非常に重要だと思っています。それがないと、ただ辛いだけになってしまい、良いプロダクトを生み出すことにも繋がりませんから。
岩城: その「楽しむ」姿勢をチームに示すために、何か取り組んでいることはありますか?
宮川: まずは、自分自身が学び続ける姿勢を見せることです。最近ではAI技術の活用にも関心があり、モバイル開発とAIの組み合わせについて情報収集を行い、実際に手を動かして試しています。また、今後は学んだことを外部に発信していくことにもチャレンジしていきたいです。ディップは、社内外への情報発信に積極的なメンバーが多く、その外向きな姿勢に感銘を受けています。自分もそうした活動を通じて、チームメンバーに良い影響を与えられればと考えています。
挑戦し続けるエンジニアへ
岩城: 今後、エンジニアとしてどのようなビジョンを描いていますか?
宮川: まずは、今関わっている新規プロジェクトを成功させることです。その上で、モバイルアプリ開発者として技術力の底上げを図りながら、将来的にはアプリだけでなく、バックエンドやインフラも含めたシステム全体のアーキテクチャを理解し、技術的な指針を示せる存在になりたいと考えています。
岩城: 最後に、ディップで働くことに向いているのは、どのような人だと思いますか?
宮川: ディップは事業会社なので、技術だけではなく「ユーザー視点」を重視できる人が向いていると思います。企画やデザインなど、開発部門以外のメンバーとも積極的にコミュニケーションを取りながら、プロダクトをより良くしていこうと考えられる人ですね。 また、現在のプロジェクトでいえば、目の前の課題解決だけでなく、5年、10年といった中長期的な視点で設計や技術を考えながら開発に取り組める人が活躍できる環境です。