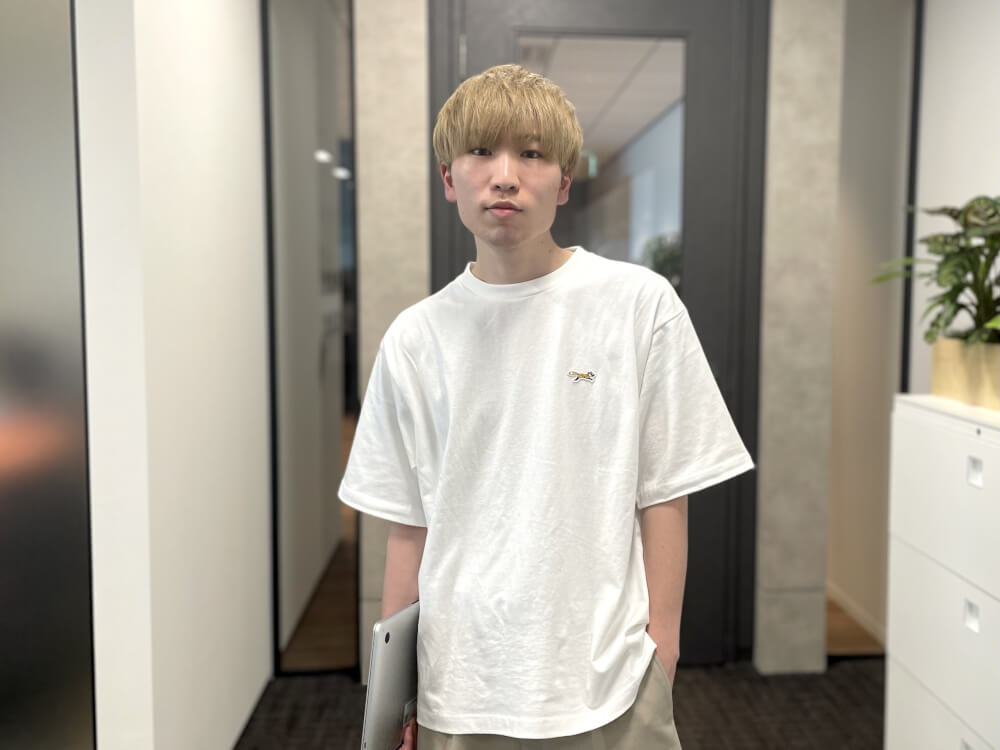職種の壁を越える好奇心。「共創」で生み出す未来のユーザー価値。
「働く喜びと幸せを感じられる社会」の実現を目指すディップ。今回は、バックエンドエンジニアとして、常に挑戦と成長を続ける佐藤薫さんに話を伺いました。ウェブデザインからエンジニアへとキャリアを転換し、現在は新規プロジェクトの開発に参画している佐藤さん。彼のキャリアパスを辿りながら、目指す「共創」の未来について深掘りします。
「好き」を実感しエンジニアへ
岩城: 佐藤さんは、大学時代からエンジニアを目指されていたのでしょうか?これまでのキャリアの歩みについて教えていただけますか。
佐藤: 実は最初からエンジニアを目指していたわけではありません。大学では学外活動に重きを置いていて、色々なことに挑戦していました。その一環で留学も計画していたのですが、コロナ禍で中止になってしまいまして。半年ほどかけて準備していたので、何か新しいことを始めようと思い、ウェブデザインを学んでみようと東京に来ました。
岩城: そこでウェブデザインに触れたのですね。
佐藤: そうなんです。ただ、ウェブデザイン、というかデザインそのものが自分にはあまり向いていないと感じ始めたんです。それよりも、学んだ知識を使って「こんなものを作りたい」という具体的なアイデアが湧いてきて。しかし、それを実現するにはデザインだけではなく、プログラミングが必要だと気づきました。
岩城: それがプログラミングとの出会いだったのですね。
佐藤: はい。そこで、海外の大学が無償で公開している「CS50」というカリキュラムに出会いました。最初は2日かかるような難しい課題もありましたが、毎日寝落ちするまで夢中になっていましたね。飛行機の移動時間中もプログラムを書いていたりして、「ああ、これが本当に好きなんだろうな」と実感しました。それがエンジニアになったきっかけです。
岩城: デザインからプログラミングへ。その転換は、やはり「好き」という気持ちが大きかったのですね。
佐藤: その通りです。特に当時、英語学習アプリを作っていて。それを形にするためにはプログラミングが不可欠だと分かったんです。
岩城: プログラミングを学び始め、エンジニアになろうと決意された中で、ディップへの入社を決めたきっかけは何だったのでしょうか?
佐藤: エンジニアになろうと決めてからは、どの業界で働くか、すごく悩みました。仕事としてやるなら、どんな社会課題に向き合いたいのかを徹底的に考えたんです。面接の時にも話したのですが、大学時代に「人生は夏休み」という言葉をよく耳にしますよね。確かにそうかもしれないと思う一方で、それって社会に出たら真っ暗だ、という意味合いに聞こえてしまって。
岩城: 社会人として働くことに、ネガティブなイメージを持たれてしまっている、ということでしょうか。
佐藤: そうです。だから、「それでいいのかな」という疑問がずっとありました。少しでも社会を良くするためにアプローチできたら楽しいだろうな、と考えていました。そこで、就職活動の軸として「魅力的な大人で溢れる社会」を目指せる事業領域を持つ会社を探し、ディップに出会いました。
岩城: ディップに決めた決定的な要因は何でしたか?
佐藤: 決め手は、本当に「人が良かった」ことです。当時の人事の方が、エンジニア採用を任されてから自主的に技術的な勉強もされていて。その方のことをすごく尊敬しましたし、就職活動の過程で出会うどの方も素敵な方ばかりでした。実際に、入社してからもそれは共通して感じています。
岩城: ディップに入社される方は、皆さん「人が良い」という点を挙げられますね。
佐藤: はい、私も全く同じです。入社してくる人たちも同じ理由でディップを選んでいるので、本当に素晴らしい環境だと感じています。
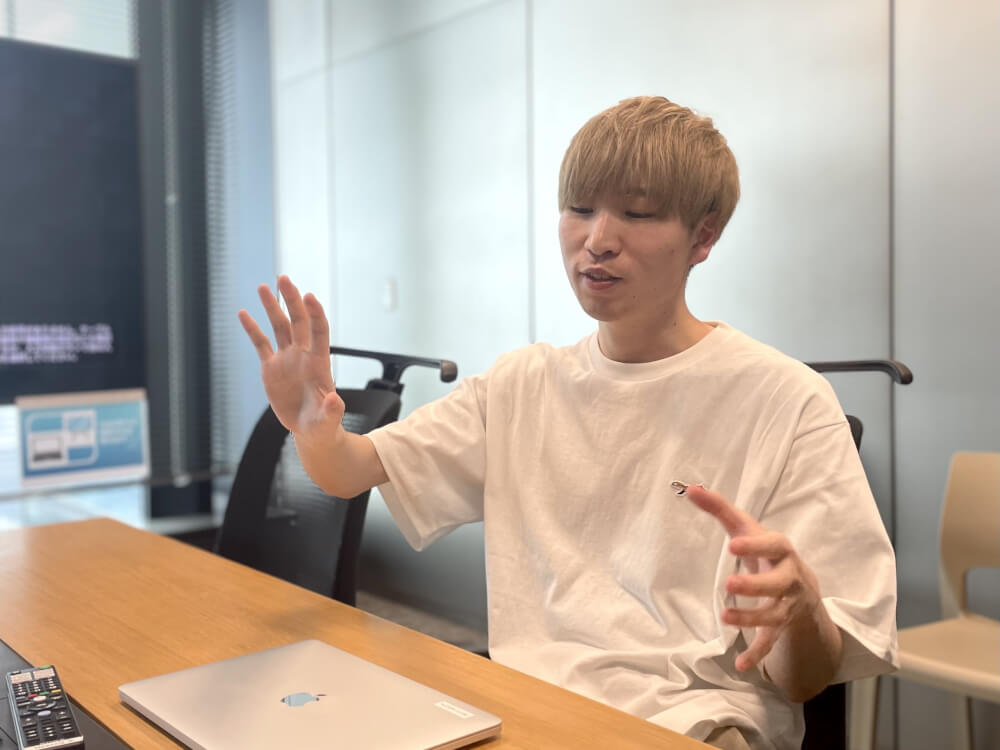
バックエンドエンジニアへの転身と「自己変容伴走支援」で得た気づき
岩城: 現在、佐藤さんは入社3年目ということですが、どのような業務を担当されているのでしょうか?
佐藤: 現在は大規模な新規プロジェクトに携わっています。6月頃から本格的にプロジェクトが動き出し、様々なチームがある中で、私はバックエンドのAPIチームとしてスクラム開発を進めています。
岩城: 具体的にはどのようなフェーズなのでしょうか?
佐藤: まだチームが発足したばかりなので、インセプションデッキの作成や技術選定を進めている段階です。インセプションデッキというのは、みんなで議論を進めていくための拠り所となる原点を明確にするためのものですね。自己開示ミーティングなども行い、これから本格的に開発をスタートする準備をしています。
岩城: まさに立ち上げフェーズなのですね。今後の開発で取り組んでいきたいことはありますか?
佐藤: はい、ドメイン駆動設計の考え方を取り入れたり、AIコーディングの進め方を検討したり、MCPを使ったりと、非常に忙しくなりそうだと感じています。今のプロジェクトに入る前は、約1年半在籍した部署と、その後の半年弱いた部署がありました。実は内定時はフロントエンドエンジニアとしての内定だったのですが、内定者時代に上長からGo言語をやってみないかと声をかけていただき、そこからサーバーサイドエンジニアとしてキャリアをスタートしました。
岩城: 内定者時代にサーバーサイドへ転換したんですね!
佐藤: 大学時代からウェブデザインを学んでいたので、エンジニアになるにはフロントエンドが自然な流れだと考えていました。ただ、私自身はサーバーサイドをやりたい気持ちがあったので、ちょうど良い機会だと感じました。
岩城: 具体的にはどのような開発に携わってこられましたか?
佐藤: APIの開発を中心に担当していました。印象的だったのは、ある障害の恒久対応として作成したバッチ開発です。アーキテクチャ設計からLambda実装、パイプライン整備、リリースまで一貫して携わらせていただきました。その他、社内での勉強会やアドベントカレンダーなど、楽しそうなことには積極的に参加してきました。
岩城: 佐藤さんは、ご自身のキャリアを主体的に選択し、挑戦されている印象を受けます。入社後、エンジニアとして「こうなりたい」という軸やビジョンはありましたか?
佐藤: 最近、「行動変容の習慣化を通じて、業務パフォーマンスと人生の納得度を同時に高めること」を目的とした、「自己変容伴走プログラム」という支援をいただいているのですが、このプログラムで、リーダーシップについて深く考える機会が多くありましたね。「自律と共創」がコミュニティのテーマです。
岩城: 具体的にどのような気づきがあったのでしょうか?
佐藤: この2年間、本当に一人でできたことは何一つなく、周りの皆さんに支えられて一つずつ実現できたと感じています。だからこそ、一人では成し遂げられない大きなことを、他者と一緒に成長しながらどう実現していける組織にできるか、ということを考えるようになりました。組織課題としても重要ですし、自分自身も大きなことを成し遂げるためには不可欠だと感じたタイミングでした。今は、そこを深掘りし、実践を増やしていく段階だと捉えています。
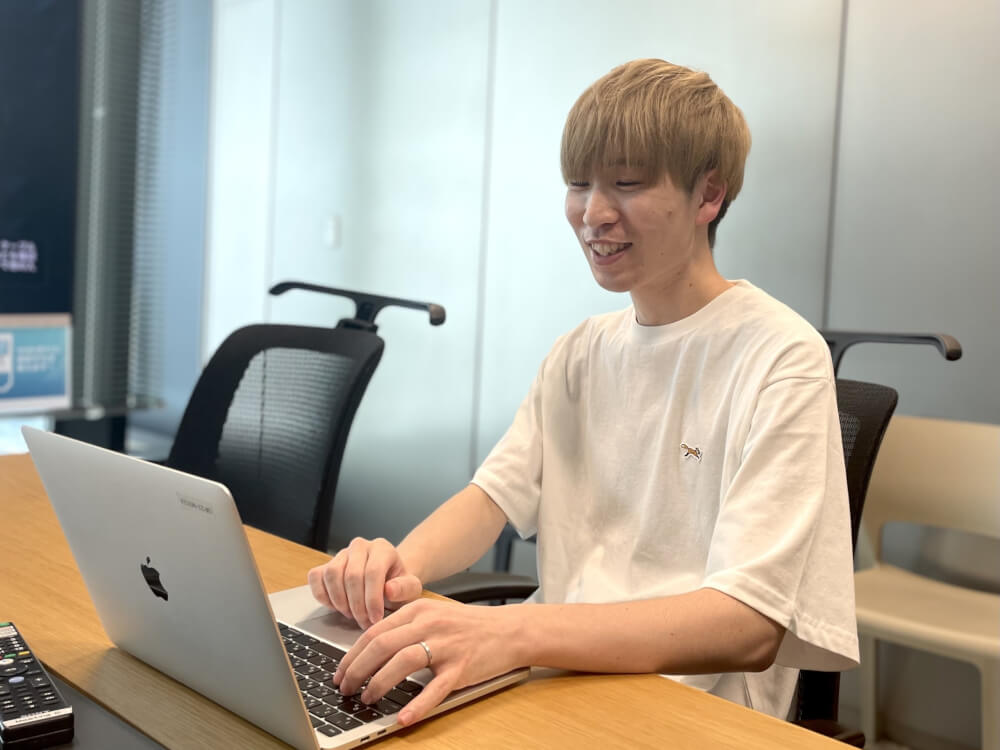
エンジニアだけでは完結しない。「楽しい」を原動力に自らが「共創」の輪を広げる
岩城: 佐藤さんはこれまで、社内外問わず様々な方と繋がりを持ったり、コミュニティ活動にも積極的に参加されたりしている印象があります。そうした行動のきっかけは何だったのでしょうか?
佐藤: やはり、私自身が大した人間ではないからこそ、何かを成し遂げようと思った時に、本当に周りに支えてもらった経験があるからです。何かをやっていくためには、他者との協業が不可欠だということを痛感しているからだと思います。
岩城: 登壇されたり、LTをされたり、積極的に前に出ていらっしゃるので、てっきり自信があるからこそ、なのかなと思っていました。
佐藤: いえいえ、全くそんなことはありません(笑)でも、単純にそういった活動が楽しいから、というのが大きいです。仕事として「楽しい」だけで良いのか、という視点もあるかもしれませんが。あとは、最近特に感じるのは、ディップの「誰かが何かを始めた時にポジティブに後押ししてくれる文化」が大きく加速していることです。
岩城: 異業種の方との交流も積極的にされていると伺いました。
佐藤: はい、「ご飯行きましょう」と積極的に誘っていますね。色々なことを知りたいという気持ちが強いので、エンジニアに限らず、直近では営業職の方や企画の方にもいろいろお話を聞かせてください!と伝えています。
岩城: 一人で仕事をする環境を好む方も多い中で、佐藤さんのように積極的にコミュニティ活動をされているのは珍しいと感じます。
佐藤: そうですね。良くも悪くも、私は技術タイプというよりは、「こういうものを作りたい」という起点でプログラミングを学び始めた人間なんです。だから、誰かに必要とされるものを作りたいと考えると、エンジニアだけでは完結しないと理解しています。企画の方も、営業の方も、様々な視点を知っておく必要があると考えているので、そこからくる思いが大きいのかもしれません。
岩城: そのような様々な分野の知識を得ることが、エンジニアとしての仕事に活きることはありますか?
佐藤: まさに、そうした取り組みを組織としても、個人としても進めていこうとしている段階です。例えば、ドメイン駆動設計という考え方では、「要望を受け、技術的な変換を行いコードに落とし込むこと」を繰り返すことで蓄積する認識齟齬を防ごうとしています。最近は、企画の同期と一緒にその関連書籍を読み合わせしようと話しているところです。
岩城: それは素晴らしい取り組みですね。
佐藤: あと、直近で感じたのは、営業さんのことを知らないと、今の業務では立ち行かないことが多くて。そのことをCTOに伝えたら、「営業同行してきなよ」と言っていただけたので、近いうちにこれから福岡で協力してくれる営業さんと同行して、現場の声を聞きに行きたいと考えています。
岩城: 現場のエンジニアがクライアントと直接話す機会は珍しいですよね。
佐藤: そうですね、これからを考えた時に、絶対に必要になると考えています。ディップだと『スポットバイトル』の開発チームがやっていた印象です。以前、救急に関するアプリを作っている会社の事例を聞いたのですが、現場のことを知らないと、いざという時に本当に役立つアプリは作れない、という話がありました。形は違えど、それは私たちにも当てはまるな、と思ったのがきっかけです。
「カオス」を楽しむ。変化の時代を共創する仲間と共に
岩城: 現在のプロジェクトやディップでの仕事を通じて、どのような「やりがい」を感じていますか?
佐藤: 今、参画しているプロジェクトは、非常にカオスな状況ではあります。しかし、だからこそ誰か一人の頭の中に「唯一の正解」があるわけではなく、みんなで「あるべき姿」を考えていける、という感覚が全体的にあるんじゃないかな、と思っています。それが、何よりも楽しいです。
岩城: やはり「楽しい」が佐藤さんの原動力なのですね。
佐藤: そうですね。私が尊敬している人たちも、よく「楽しめるかどうか」という話をしていますから、私もそうありたいと思っています。
岩城: 今後、エンジニアとして、また組織の一員として、どのようなビジョンを描いていますか?
佐藤: まだまだ道半ばですが、ゆくゆくは本当にユーザー価値を軸に、自律的にチームを牽引していき、組織に良い影響を波及させるような存在になりたいと思っています。そうした組織になれば、みんなが同じ方向を見てものづくりが加速し、一人ではできない大きなこともどんどん成し遂げられるようになるはずです。そのために今は、プロジェクトやチームの成功のためにできることを日々探し、小さな施策を繰り返して実行サイクルを回している段階です。
岩城: 佐藤さんは常に、個人やご自身のチームだけでなく、組織全体や会社のことを自分ごととして捉えていらっしゃるように感じます。それは、佐藤さんの性格によるものなのでしょうか、それとも何か強い信念があるからなのでしょうか?
佐藤: 直近で腹落ちしたことがあるのですが、社長が「成長環境をこれからも作っていく」とおっしゃっていました。人生において成長は不可欠で、成長環境をどんどん作って成功していける組織になったら、そこで求められることや、やりたいことが増えていく。それは個人の成長にも繋がる。つまり、組織の成長と個人の成長は、同じ方向を向いている、という考え方です。このお話を受けて、まさにその通りだと感じました。
岩城: 最後に、この記事を読んでいる候補者の方々に向けて、佐藤さんの視点から「こんな人ならディップで活躍できそう」「こんな人なら向いている」というメッセージをお願いします。
佐藤: 今は非常に変化の激しい時代だと感じています。だからこそ、その変化を楽しみ、そして「共創」という視点を一緒に意識していける人と働きたいです。これまでお話ししたように、ディップには職種に関係なく同じ方向を向いて、様々なことを「共創」していこうとする仲間がたくさんいます。ここにワクワクする人と一緒に働けたら、さらに楽しくなるんじゃないかなと思っています。