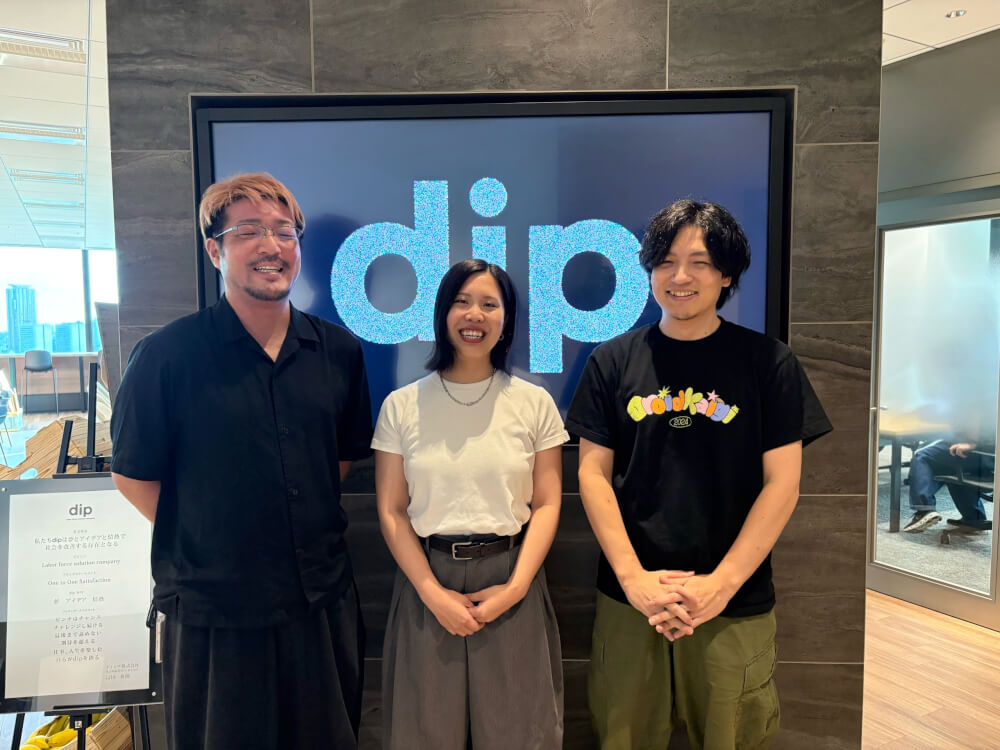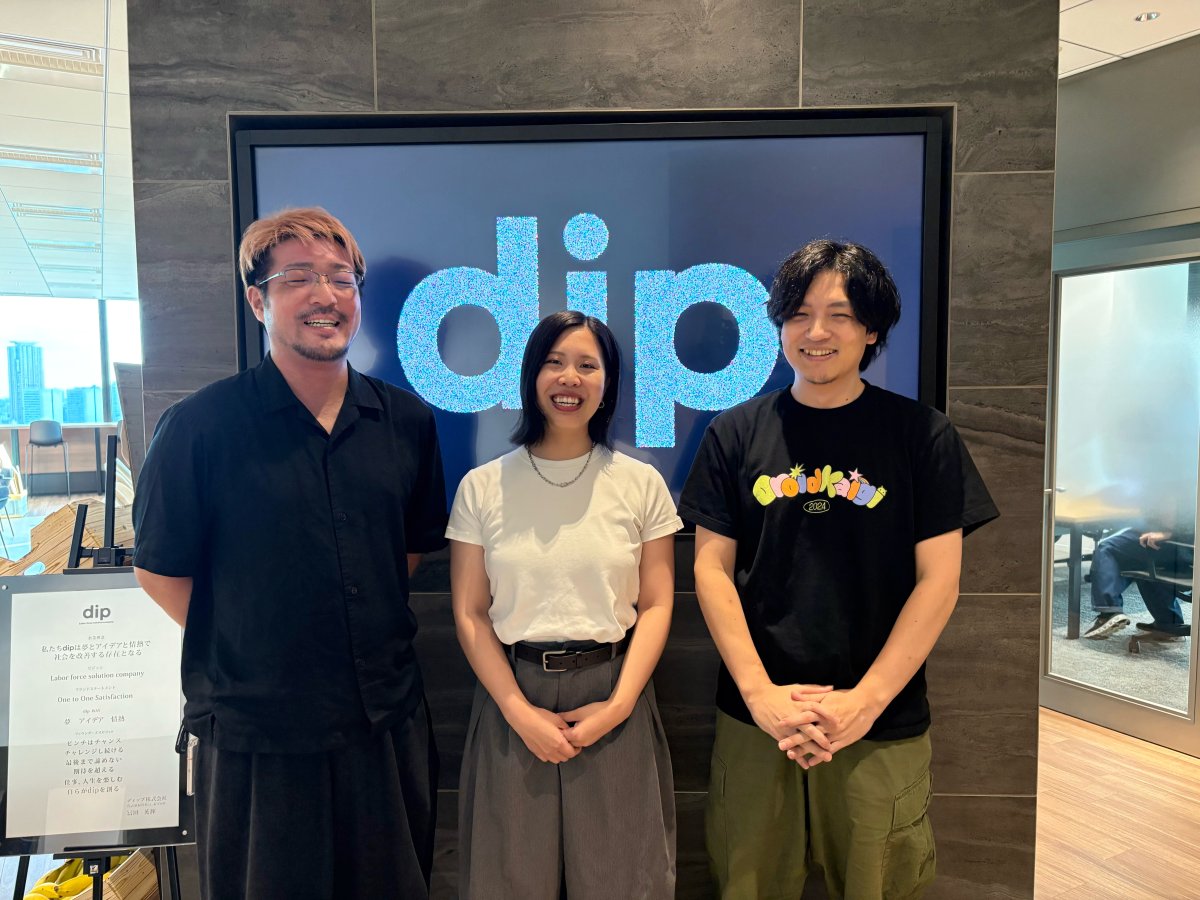
「失敗を恐れずとりあえずやってみる」組織へ。アジャイル推進課の3人が語るディップ版スクラムガイド誕生までの道筋。
ディップではスクラムの手法を組織全体に広めるため、「ディップ版スクラムガイド」を作成しました。今回は、そのガイド作成を主導したスクラムマスターの大瀧純平さん、毛利修人さん、梶原萌恵子さんの3名にインタビュー。この3名は2025年10月4日(土)にスクラム祭りの鹿児島トラックでも登壇します。なぜこのガイドが必要だったのか?そして、どのようにして完成までたどり着いたのか?プロジェクトの裏側と、彼らが考えるディップの未来について語り合います。
スクラムマスターが集まるアジャイル推進課が始動
岩城: まずは皆さんの自己紹介と、所属部署について教えてください。
大瀧: プロジェクト推進部アジャイル推進課の課長を務めている大瀧です。今は兼務で『スポットバイトル』チームにも所属しておりスクラムマスターをしています。
梶原: 同じくアジャイル推進課の梶原です。私は兼務で『スポットバイトル』のアプリとWebチームでスクラムマスターを担当しています。
毛利: 同じくプロジェクト推進部アジャイル推進課に所属している毛利です。兼務で『バイトル』のスマートフォンアプリチームでスクラムマスターをしています。
岩城: 皆さん兼務なんですね!所属するアジャイル推進課は、具体的にどのような役割を担っている部署なのでしょうか?
大瀧: アジャイル推進課は、開発本部内にいるスクラムマスター全員が集まっている組織です。各チームの状況を標準化し、ディップとしての開発標準を作っていくことをミッションとしています。そうすることで、開発組織全体のアジリティ(俊敏性)を高めていこうという狙いです。
毛利: 以前からアジャイルは推進していましたが、部署やチームごとにナレッジが分散しているという課題がありました。そうした情報を集約し、より効果的に共有していくために、専門性の高いスキルを持つスクラムマスターが、チームトポロジーにおけるイネーブリングチームのような位置付けとして部署が発足したと認識しています。
「ディップ版」だからこそ意味がある。迷わず進めるガイドに
岩城: 今回作成された「ディップ版スクラムガイド」は、どのような経緯で生まれたのですか?
大瀧:もともとは、ディップのアジャイル開発を支援してくれる外部コーチ、株式会社レッドジャーニーの森實さんのアウトプットとしてディップ向けスクラムガイドの作成を検討されていたそうです。ただ、支援を行なっていたチームのスクラムマスターが、ディップ独自のスクラムガイドのベースを作ってくださったんです。そこからそのスクラムガイドをブラッシュアップして形にしようと動き始めました。今回のように組織のスクラムマスターが主体となって自主的にガイドを作り上げたのは、これまでの支援の中でディップが初めてだったと言っていただけました。
梶原: また、それと並行して森實さん含めスクラムマスター同士の相談会を実施していました。そこで集まった課題やナレッジも、このガイドを反映しながらブラッシュアップしていくことで、知識を体系化していこうとなりました。
岩城: 既存のスクラムガイドは、すでに世の中にありますよね。なぜ、あえてディップ版を作る必要があったのでしょうか?
大瀧: スクラムガイドは非常に抽象度が高く書かれているため、初めてスクラムに触れる人が読んでも、何をすれば良いのかが分かりにくいんです。そこで「僕たちはこう解釈して、こう始めました」という具体的な実践例を示すことで、初心者でも迷わずに実践できるようにすることが目的でした。
毛利: まさにその通りで、正しいスクラムというよりは「分かりやすいスクラム」を目指しました。例えば、スプリントの期間は「1週間でやってみましょう」と推奨期間を明記したり、具体的な失敗例やそこから得た教訓も盛り込んでいます。そうすることで、正しいかどうかを考えるよりも、まずは迷わず一歩踏み出せるように工夫しました。
重要なのは「とりあえずやってみる」事。失敗がない=停滞
岩城: 本業の傍らでガイドを作成するのは大変ではないですか?
大瀧: まずやってみようという事で週に1回、1時間のミーティングを設定し、3人でブロックごとに分担して作業を進めました。修正すべきコメントを残しておき、各自が1週間で修正を終える。それを次のミーティングでレビューして、また次の担当を決める…というサイクルを回していました。これもアジャイルですね(笑)
毛利: 全体のロードマップを立て、8月末には完成させたいというゴールを設定したことで、程よいプレッシャーを持ちながら進められたのが良かった点だと思います。
梶原: 誰も「やれ」と言ったわけではないので、期限がなければ後回しになっていたかもしれません。程よい強制力があったからこそ、うまく進んだのだと思います。notionで作成していたので他の2人の作業を見て「やらなきゃ」と思えました(笑)

岩城: やれと言われていない事を進めて形にするって難しいように思います。何がモチベーションだったんでしょうか?
梶原: 実は私自身スクラムを始めたのは2024年の10月頃なんです。経験が浅い分、自分が学ぶためにもこの機会は貴重でした。また、自分たちが最初にぶつかった課題や失敗をナレッジとして共有することで、他の人たちが同じ失敗を繰り返さないようにできるのは、とても意味があることだと思っています。
毛利:僕もスクラムの経験は2024年の5月からなので、自分が学ぶために参加していたのが大きいですね。自分の知識を整理できるだけでなく、「他のチームはどうしているんだろう?」という疑問を解消する場にもなりました。ディップにはアジャイルを必要としている人がたくさんいるという感覚があったので、自分たちがやるべきことだと感じていました。
大瀧:僕は、スクラムの経験は元々長くありましたが、アジャイルそのものを言語化し、アウトプットする経験がなかったので、このプロジェクトは非常に良い機会でした。言語化することで自分の中の知識が整理されましたし、何より「やろう」と声をあげた時に2人がついてきてくれたので、面白そうという気持ちで流れでスタートしました(笑)
岩城:スクラムを学ぶ中で一番重要だと感じる事はありますか?
大瀧:とりあえずやってみる事です。とりあえずやってみて、振り返りをする事で今後の見通しがついたり、これは違ったねって事でじゃあ次どうしようかと考え直すきっかけにもなりますし。僕らのチームの答えって僕らでしかありえないんですよ。外部の事をいくら勉強しても、やった結果でしか答えって出ないと思うのでとりあえずやってみて合うか合わないかを考えるんです。
梶原:実際失敗した事もありましたね(笑)プロジェクトの初期段階では、インセプションデッキなどの手法を「とりあえずやってみよう」と進めてみたものの、準備不足や進め方が固まっていなくて上手く行かなかったりとか。でも、ここから「なぜやるのか」という目的やゴールをしっかり定めることの必要性に気づけました。
毛利:失敗できてるって成功だと思うんです。動けていなかったら失敗すらできないと思うので。なので逆に失敗がない週の方が不安でした。なんとなく1週間が過ぎていくような感覚になりますね。
大瀧:何も発見できなかった・・・ってなります(笑)
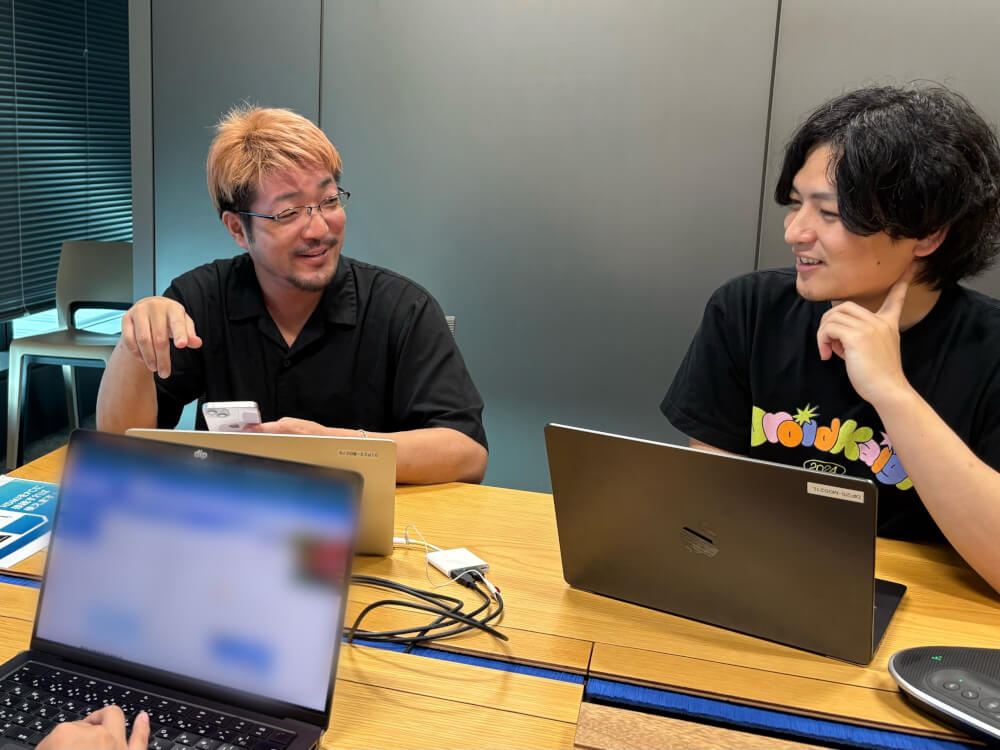
プロダクト開発の標準化に向けて
岩城:今回初めて作成したディップ版スクラムガイドですが、今後どうなっていって欲しいと感じていますか?
大瀧:開発本部全員の知見になって欲しいです。多分、現時点でこのスクラムガイドが自分たちのものだって思っているのって僕ら3人しかいなくて。「スクラムね」「あ〜こんなのやってる人たちがいるんだ」みたいな。でもこのスクラムガイドに完成は無くて、皆で作っていくものだと思っています。全員が自分のものだと思ってどんどんコメントしたり気付きを貯めていったりそれが採用されて変化していったり。
梶原:自分ごとになっていって、常に進化していけるのが理想ですね。そして今後初めてスクラムを導入する組織で最初に読んでもらえるものになって欲しいです。
岩城: 今後ディップの開発組織がどうあるべきか、ビジョンはありますか?
毛利:結局スクラムって手段だと思うので、実現したい事に向けてスクラムではない別の手段があるならそれで良いと思うんです。でも経験主義みたいな部分は文化にしていきたいですね。スクラムかそうでないかは関係無くて、失敗しながら経験して振り返ってすぐ適用していくっていう、チャレンジできる組織になっていったら良いと思います。その手段の一つとして僕たちがアジャイルを推進していくという役割だと思っていますね。
大瀧: とりあえずやってみる、は本当にそうですね。ディップの開発組織の課題でもあると思うんですが、上司と部下が何かを並走しながら作っていくってあまりないんです。上司部下じゃなくても、同期でも他部署でも、「一緒にやってみようよ」って言える組織になっていって欲しいし、そういう文化が広まって欲しいと思っています。
梶原: 私もお2人の考えに同意ですね。ディップは今まで縦割りの開発が多かったと思います。スクラムはあくまで手段ですが、企画側も開発側も横のつながりができて組織としてどんなプロダクトを提供していくのか考えられるようになり始めた今の組織が土台作りのフェーズ。この土台を強くしていってさらに成長できたら事業としても進化していけると思っています。
岩城:ありがとうございます。