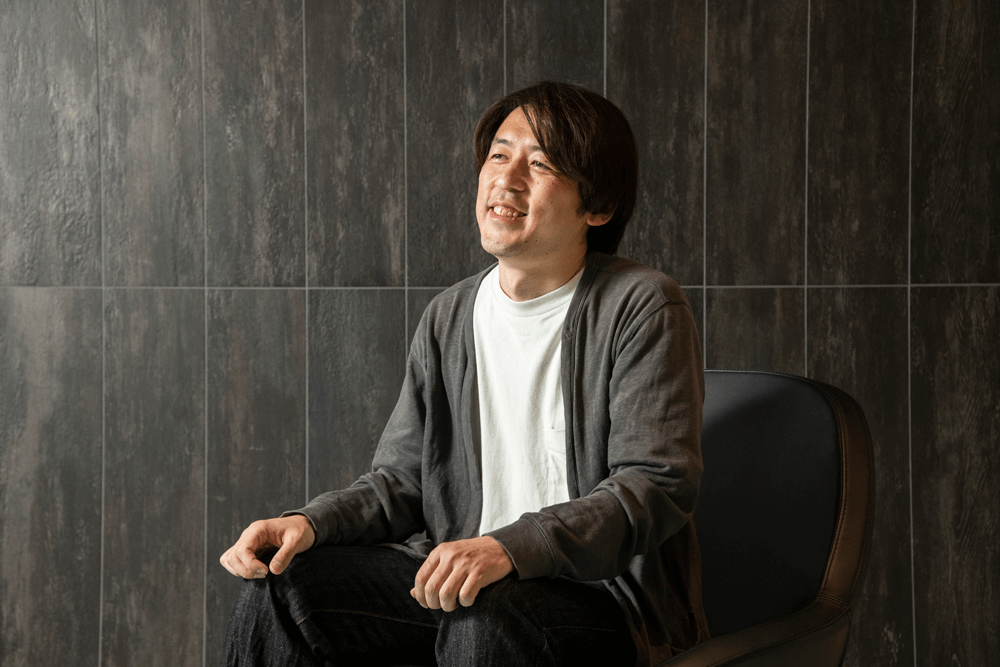
CTOが語る、ディップエンジニア組織と採用のこと。
ディップでCTO(最高技術責任者)をやっている豊濱です。この1年、いろいろなところでエンジニア組織や、採用についてお話してきましたが、改めて自分の言葉でお伝えしたいと思います。
エンジニアとは不思議な生き物である
もう20年以上Webエンジニア業界でお世話になっていますが、今も昔も「エンジニアの成果は時間で計れない」と考えています。年齢や年次に関係なく、各々が持つ経験・スキルによって成果の違いが出やすい職種です。
スキルの高いエンジニアほど短時間で成果を出せるため、人数×時間(人月)で規模や工数を計ると実態とかけはなれていきます。よく言われる、エンジニアが100人いれば100人月だと見積もられた案件が1ヵ月で終わるのか、というお話ですね。
そもそも成果とはなんなのか?
ディップのような自社でプロダクトを運営している会社の場合、ただ「作る」だけではエンジニアの成果として充分とは言えない、と考えています。
仕様や要件に沿って何かを作ることができるのは当然として、その先にある「このプロダクトの存在意義・目的」を理解し、その目的に近づくため、存在意義をより明確にするために
・これまでより速く
・楽に到達できる方法を
・提案できる
というのが成果と定義しています。
あくまで例ですが、「会員登録をしてもらい、キャンペーンの告知ができる機能を作ってほしい」というものがあったとき、ゼロから作ろうとするとそこそこの重さの開発になりそうですが、その目的が「キャンペーンに応募した人しか見られないページを作りたい」だったらどうでしょう。URLの複雑化とnoindexだけで事足りるかもしれません。
・チーム開発ができる
・多職種のチームでコミュニケーションが取れる
・提案できるだけの知識や経験をもっている
・またはモチベーション高くインプット・アウトプットに取り組める
プロダクトを構築・改善するチームメンバーとして、自分が持つ知識・経験をもとにアウトプットできる存在でいてほしい。役割がエンジニアとして開発するだけではない、というイメージです。
ディップの現在地
そんな理想はあれど、いまのディップのエンジニアやプロダクト開発ってどうなの? と言われると、まだまだ過渡期です。いま目に見えているところだけでも課題や改善点はたくさんあるし、その先のぼんやりした部分でもやりたいモノ・コトは山積みです。
エンジニアリングだけじゃなく、他職種も含めたプロダクトの開発フロー、エンジニアの社内での存在感や、制度設計、組織の構築についても、正直なところまだまだ整備できているとは言えず、これから整えていく段階にあります。
とはいえ、いまのままこれから5年〜10年を過ごすのは、もっと大きな課題を生んでしまいます。
おこがましいようですが、自分がディップに入社してからのこの1年だけでも、解決できていない課題はありつつも、ものすごく大きな変化ができたと思っています。
・社内にエンジニアがいることの価値
・バイトル、はたらこねっと、コボットのようなプロダクトにもっと最適な開発フローがあるのでは、という考え方
・エンジニアを含めたものづくりをする職種に最適な制度設計が必要なこと
こういうことが当たり前に話せるようになってきたな、と感じています。
これから一緒に、次のディップのエンジニアリング、エンジニア組織を作ってみたい、という人がもっと増えてほしい、と考えて、採用活動のアクセルを思いっきり踏んでいます。
自分がいなくても回る組織に
自分が入社した当初から社内でお話していることです。
この1年は、僭越ながら自分が主導して、採用計画、組織設計、システム刷新、エンジニア(ものづくり職種)向け制度設計、プロダクト開発効率化(のための指標作成、ウォッチ、対外交渉、開発手法)、セキュリティなど、いろいろなものに取り組ませていただきました。
ここからは2025年に向けて、採用を進め、各役割を担当する人材が効率よく回るフローや仕組みを整備し、「自分がいなくても回る組織」を構築していきます。結果、最終的にCTOを次の世代に渡せるところまでいけたら、1つのゴールかな、と考えています。
これからのディップを一緒に作りましょう。






