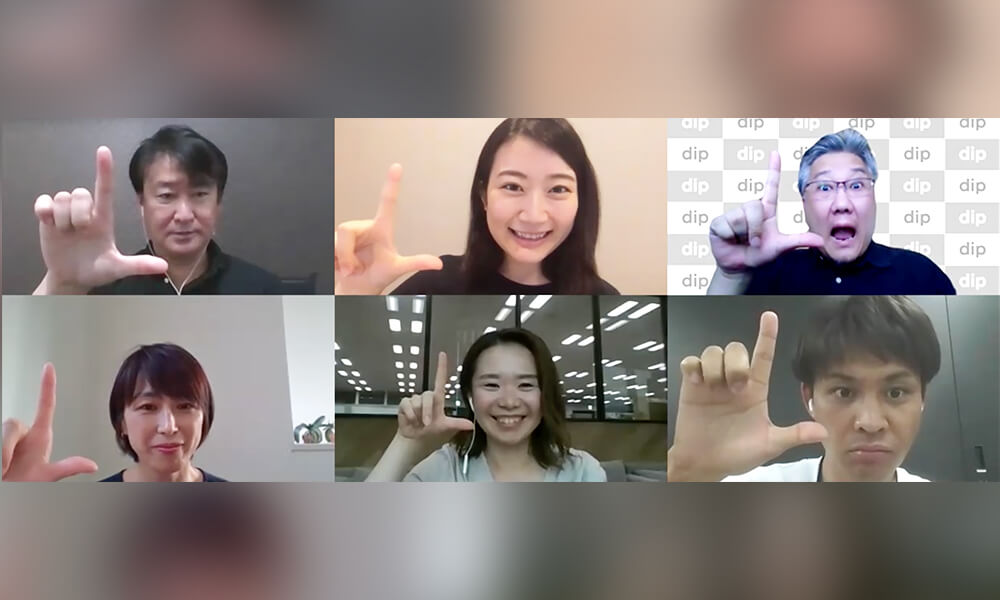
【社員対談】経理も総務も動画撮影?!社員総出で実現した「動画求人サービス」を振り返る。
ディップは、 2010年8月、バイトル(当時「バイトルドットコム」)にて業界初となる動画サービスを開始しました(当時のリリース)。動画サービスはどのような経緯で生まれ、開発部隊・営業現場では何が起こっていたのか。そして、そこから見える「ディップらしさ」とは。当時を知る社員(&元社員)に話を聞きました。
世はまだガラケー時代。そんなときに突如スタートした「動画」サービス。
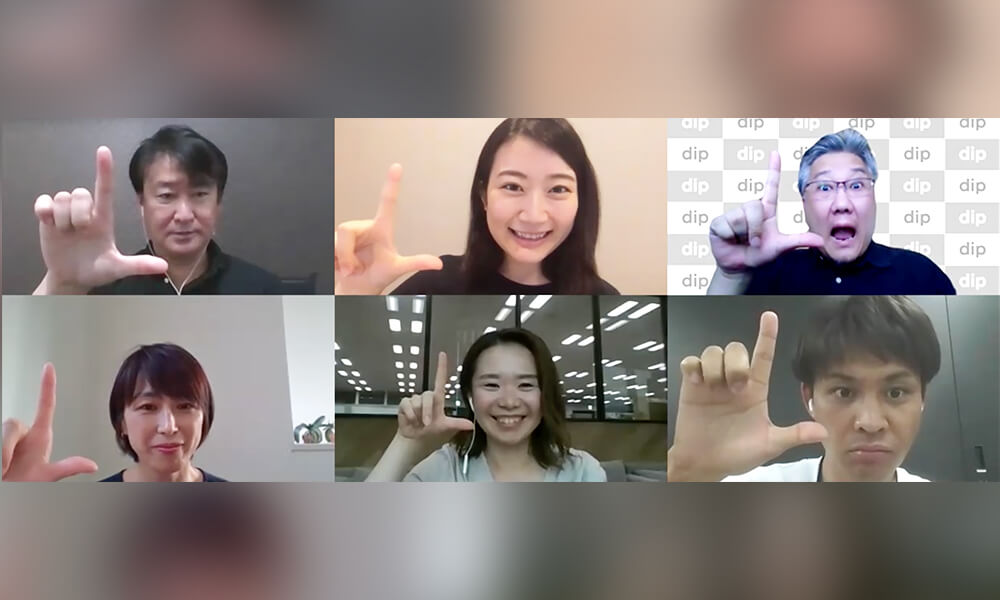
左上より時計回りに、植木、加納(人事・対談主催)、森田、西脇、朝倉、木下
高橋:僕は2008年入社なので、2010年に動画が始まるとなり社内がバタバタしたのを鮮明に覚えています(笑)そもそもはどういった経緯で始まったんでしょうか?植木さんは当時から商品開発本部長だったかと思いますが、いかがですか?
植木:2010年頃のディップには「紙媒体にはできない、ネット媒体だからできることをやろう」という風潮がありました。第1弾として6月に各求人への応募状況が分かる「応募バロメーター」という機能をリリースし、第2弾で「動画」の企画を進めていました。紙媒体だと写真は載せられるけど、動画は絶対に載せられない。それにモバイルシフトを推進している時期でもあったので、通勤や通学の途中に仕事が探せて、そこには紙媒体には載っていない動画が載っていて、職場の雰囲気がリアルに分かる。これこそネット媒体である自分たちが目指すべきユーザーファーストなんじゃないかって。
木下:当時、私はバイトルの編集長でした。その頃は「情報の鮮度が大事」という話も出ていて、動画の方向性も、いわゆる「つくりもの」ではなく、できるだけリアルに働く場所、人、仕事の雰囲気が伝わる動画を撮影しようということで進めていましたね。
高橋:ちなみに「サイトに動画を載せる」って、技術的にはカンタンなものだったんですか?
植木:いや、ぜんぜん(笑)今みたいにAndroidとiOSの2つしかない、みたいな単純な話ではなく、当時は各社がガラケーを出し、仕様も異なっていたので、その技術的ハードルをいかにして乗り越えるかが商品開発本部としての最初のハードルでしたね。
高橋:ちなみにそれはどうやって乗り越えたんですか?
植木:もう、最後は人力で(笑)すべての端末、すべての仕様を洗い出して、それに合うASPのサービスがないかを探して、みたいな。「できるか、できないか」ではなく、「実現するためにはどうすればいいか」だけを考えて、みんなで進めていきました。
で、なんとかシステムが完成し、リリース1ヶ月前に数千件分の動画を集め、意気揚々と社長に報告に行ったら…。
高橋:行ったら…?
社員総出で撮影に。目指すは1ヶ月で全件掲載。
植木:「バイトルには何万件もお仕事が載っているのに、動画が数千件しか載っていなかったらユーザーはがっかりしないか。せっかくみんなで苦労して出すサービスなのに、逆にユーザビリティを損ねることにならないか」と厳しいご指摘をいただいて…。
高橋:なるほど…。
植木:でも社長がおっしゃることはごもっともで。自分たちの手の届く範囲で物事を考えてしまい、ユーザーファーストが徹底できていなかったな、と反省しました。
そこからは全社的にも一気に温度感が上がり、営業以外にも動画撮影用の携帯を配り、制作はもちろん、経理や総務も総出で撮影に行きました。当時の経営管理本部長も行ってましたよ(笑)
森田:このときはもう「損得勘定」とか「ふつうは」とかじゃなくて。目標に向かって何がなんでもやるしかない、という感じでしたね。
西脇:全社朝礼でも社長から「今は売上より動画を最優先してほしい」というお話があって。ホントに全社一丸となって進めていきました。
植木:リリースから10年経って、今は他の会社でも動画サービスをやっているところがあるけれど、我々のような規模感で、標準サービスとしてほぼ全案件につけているというところは聞いたことがない。それは、立ち上げ時の大変さと、運用していく大変さを、ディップだけが全社一丸となって乗り越えられたからだと思う。
高橋:僕も昨年まで求人広告の制作職をしていましたが、動画がサービスに加わってから「表現の幅」「解決の手段」が増えたように思います。「良い求人動画」なんてほとんど事例がないので、たとえばテニスコーチの求人だったらコートの端に空き缶を置いてサーブで倒せるまで撮影したり、スタッフさんに「先月の給料」を暴露し合ってもらう動画をつくったり、みんなで知恵を絞りながら事例をつくっていきましたね(笑)
植木:結果的に、リリースまでに「全件掲載」とまではいかなかったものの、1ヶ月で数万件の動画が集まり80%の案件には動画を掲載することができました。
さらなるトラブル。不具合。部署を越えて協力し、動画をスタンダードに。
植木:と、ここで終わればハッピーエンドなんだけど、実は続きがあって…。スピード優先でシステムをつくったことで、大きな不具合があり、具体的に言うと管理画面で案件を更新すると動画が外れてしまうという仕様になっていて…。
一同:…。
植木:とはいえ、毎日何万件も手作業で設定するわけにはいかない。そんなとき、「大阪の制作部に今で言うRPA(Robotic Process Automation)のようなサービスを使ってプログラムを組んで自動でやっているヤツがいるらしいぞ」というウワサが聞こえてきて。それがそこにいる森田くんなんだけど。
森田:(笑)
植木:当時森田くんはシステム開発部の所属ではなかったけど、会社の最優先事項ということで急遽東京に来てもらって、フロア2列くらいに高性能PCを何台も並べて、RPAを組んで全案件の更新作業をまかなうということをやっていましたね。で、その功績が認められ、MP(メディアプロデュース)部門に異動になり、木下さんの次にバイトルの編集長になるという(笑)
高橋:もうホントに、「全社員でなんとかしていく」という感じですね。
植木:当時、社内に作曲が得意なメンバーがいて、そのメンバーに頼んで動画で使えるBGMを10曲くらいつくってもらったりもしました(笑)
朝倉:営業としても、「求人広告の動画」という新しい価値をお客さまに伝えていく必要があって。社長が直々にオフィスをまわり、ロープレしてくださったりもしました。
高橋:リリース当初は「動画を掲載すること」が目標でしたが、クライアントの課題解決につながる動画、ユーザーにとって役に立つ動画を模索しながら、求人広告における動画をみんなで「スタンダード」にしていった感じはしますよね。
動画サービスの誕生には、ディップのファウンダーズスピリットが詰まっている。
高橋:あらためてこの10年間を振り返ってみると、ホントにいろんなことがありましたね。みなさんにとって、この経験はどのような教訓につながっていますか?
森田:ディップってこういう「祭り」みたいなことがたびたびあって。やっているときは神輿担いで太鼓一晩中叩いてしんどくて辛いんですけど(笑)終わったら楽しかったね、みたいな。
今後はこういうお祭りを「現場から」「みんなから」起こしていけるといいかなぁと思います。
朝倉:私は「新しい価値をつくる」という経験ができたのがいちばん大きかったですね。
たとえば私の部署では士業の案件を集めている最中で、現在は保育・医療、介護の案件を集めているのですが、今までどおりのやり方で求人広告を載せるだけではダメだと思っていて。世の中に対して、その職業や仕事がどれだけ価値があるものなのか、いろんな方法で伝え、イメージを変え、そこに従事する人たちを増やしていくのが今後の日本社会の活性化に繋がるのかなと思っています。そんな風に大きな視点で考えられるようになったのも、「動画」というサービスを自分たちでイチから普及させていった経験、自負があるからだと思います。
西脇:やっぱり自分たちで手掛けたサービスって、愛が生まれるんですよね。サービスも好きになるし、自ずと愛社精神も生まれてくる。
他社の真似事ではなく新しいサービスをつくるのがディップらしさだし、ディップで働く価値。今の若手メンバーも求人メディアにとどまらずRPAなどを使って新しい価値をどうやって広げるんだっけ?というまさしく僕らと同じようなことをやっていて。そうすると会社やサービスに対してロイヤリティが持てるし、愛せる商品だからこそお客さまに対してもディップでしか感じられないサービスや価値を感じていただけるのかなぁと思います。
植木:動画の一連の話って、ディップのファウンダーズスピリットをほぼすべて体現したプロジェクトだったんだなあと思います。
チャレンジし続けるとか、ピンチはチャンスとか、最後まで諦めないとか、期待を超えるとか、自らディップを作るとか、仕事を楽しむとか。まさに動画で体験したことはファウンダーズスピリットそのものだし、かつ、それができているということは、我々のDNAや、組織とか個々人の根底にコレがあるんだなぁということをあらためて感じました。
正直、今さら過去のことをほじくり返しても、とすこし思っていたのですが…。本当に大切なこと、体現していることは今のメンバーにも伝えていかないといけないなぁと思い、いいきっかけになりました。木下さんにも会えましたし(笑)
木下:私は今日10年ぶりぐらいにみなさんにお会いして、思い返してみると「楽しかったなぁ」という記憶しかありません(笑)
ユーザーファースト、Webでしかできないこと、ディップのファウンダーズスピリット、当時私が聞いていたことが今も脈々と受け継がれているんだなぁと思い、あらためてすごいなと思いました。
高橋:木下さんも、みなさんも、本日はありがとうございました!






